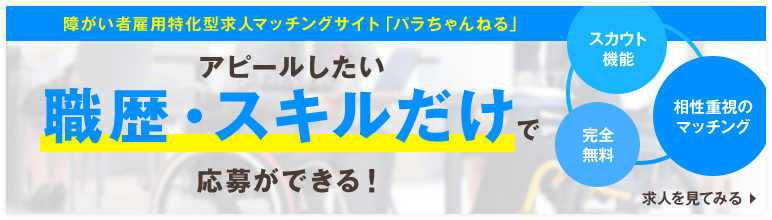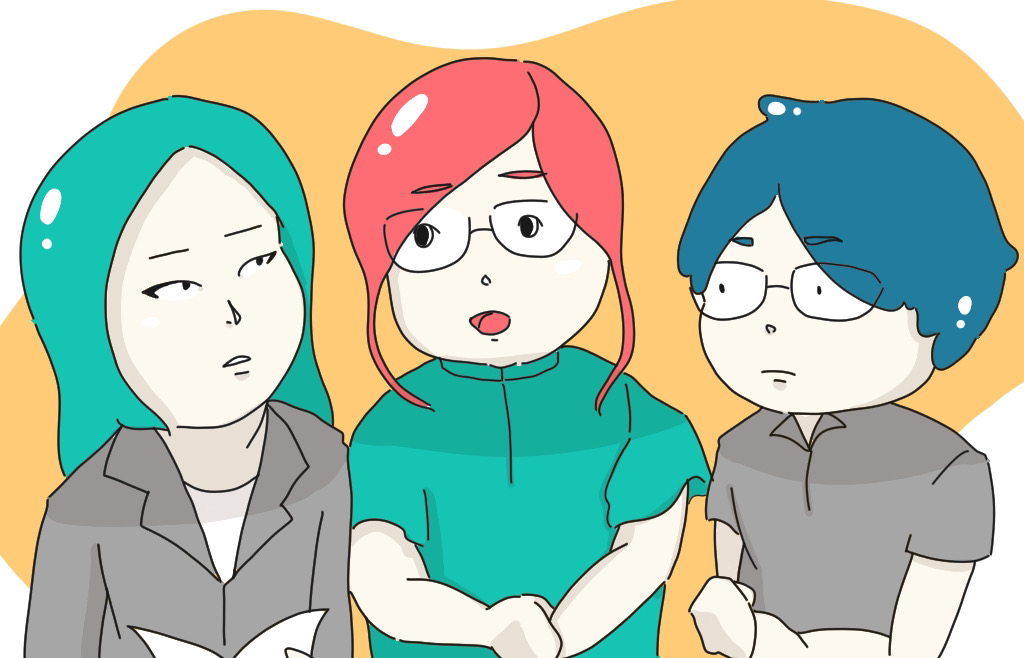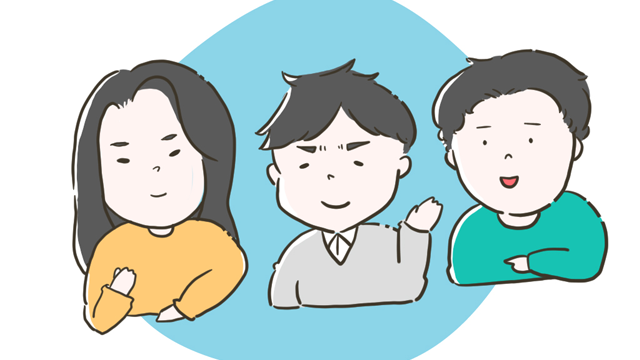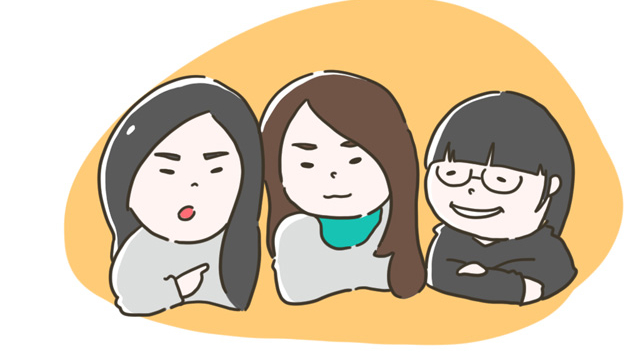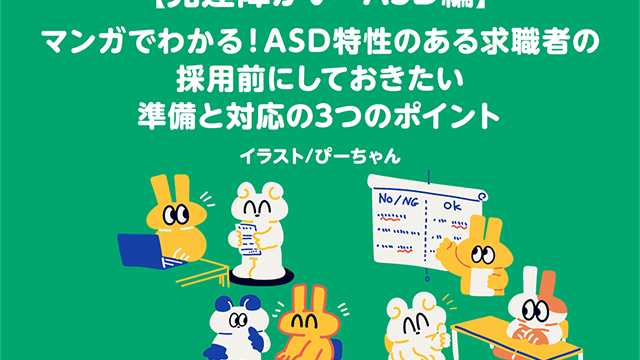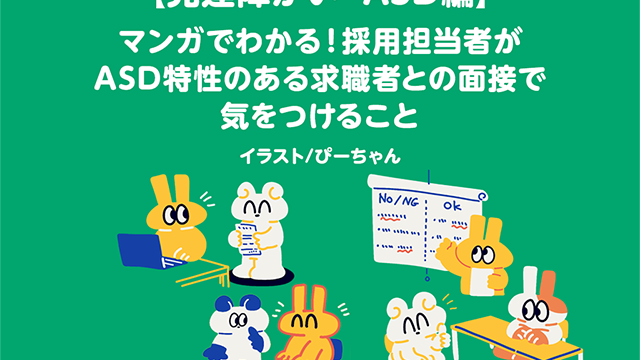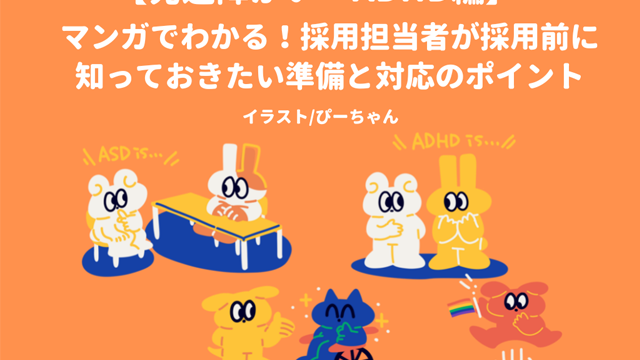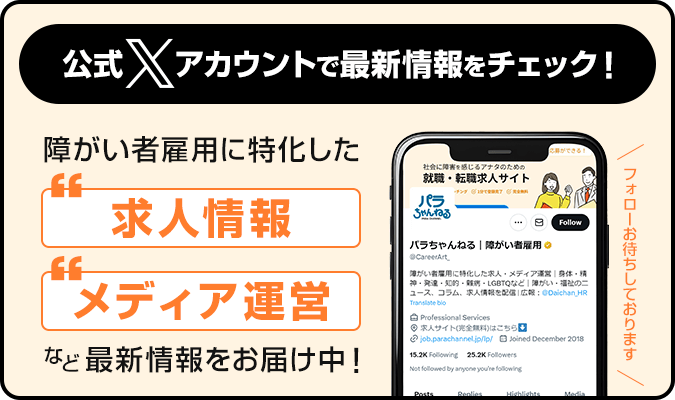こんにちは。多様性を推進するプロジェクト パラちゃんねる代表の中塚です。
今回は、採用企業の皆さまの声をもとに開催された「当事者に聞く、障がい者採用へのホンネ」セミナーについての活動レポートをお届けします。
※この記事は、2022年8月に公開されたものを再編集しています。
はじめに
多様性を推進するプロジェクト パラちゃんねるは、「誰もが特性を活かせる、多様な選択肢がある社会」を目指し、障がい者雇用の活性化を図ることで「働く」側面から社会課題の解決に挑戦しています。
2022年1月からスタートした求人サイトでは、日々、全国の採用企業の皆さまより「当事者のリアルな現状をもっと知りたい」という声が寄せられています。
- 当事者の障がい特性が正直わかっていない
- 当事者が実際にどのようなポイントで求人を見ているのかリアルを知りたい
- どんな働き方をしているのか、直接聞いてみたい
- 今働いている社員には聞けないし、、、
今回は、採用企業の皆さまの声をもとに開催された「当事者に聞く、障がい者採用へのホンネ」セミナーについての活動レポートをお届けします。
>ファシリテーター
NPO法人Collable(コラブル)の代表理事 山田小百合さん。障がいのある人たちや多様な人との共創の場をつくるCollable(コラブル)は、ワークショップを通じて「インクルーシブデザイン」の普及や、障がいの有無をこえた場作り、それらの啓発活動を行っています。
>登壇者①
発達障がい(ADHD)のある、とくらじゅんさん。社会人になって診断を受け、事務職からデザイナーに転向。現在は障がいをオープンにしながらデザイナーとして一般就労されています。
>登壇者②
難病(べスレムミオパチー)のある、山口真未さん。商業高校卒業後、障がい者雇用で大手鉄道会社に入社し、経理・人事など10年間在籍。現在はファイナンシャルプランナーとして活動しています。
セミナー当日は匿名開催ということもあり、障がい者雇用に関わるさまざまな方々に参加いただきました。
- はじめて障がい者採用をするので当事者の方の生の声を知りたい
- すでに何名か採用しているけど定着に不安がある
- 現場配属後の配慮について質問したい
- A型事業所を運営している
障がい者雇用を推進している企業の皆さまに、ぜひ読んでいただければ幸いです。
環境の変化が適性を生む
とくらさんは、事務職でのミスが目立ち、発達障がいの診断に至っています。入社後に診断を受けることで、異動ではなく退職を選択せざるを得ない方も少なくありません。職種転換に至った経緯や事務職からデザイン職に異動したことで生まれた働きやすさを教えてください。
最初の就職先は昔からの知人の会社だったため、社内でのコミュニケーションがしやすい環境がありました。加えて、当初は事務職でしたが、偶然デザイン職に空きができイラストレータ・フォトショップを扱えるとのことで、挑戦してみようと職種転向に至りました。
思い返すとデータを見る、数字・テキストを見るというのが不得意だったと感じています。デザイン職は事務職のように細かい数字のチェックや調整もなく適性を感じますし、業務で連携する人数が多いため、ミスが途中で発見されやすいという点も働きやすさを生んでいます。
現在は、発達障がいをオープンにされながら、障がい者雇用枠ではなく一般枠で就労されています。職場で受けている配慮はあるのでしょうか。
現在は2社目ですが、1社目の経験を踏まえ、社内で障がい特性は伝えています。現在はフルリモート業務に従事したことで多方面からの指示もなく、テキストのコミュニケーションが必須となるため、特別な配慮を求めなくても、不便なく働けていると感じています。

間口は広く、まずは対話
山口さんは、高卒で大手鉄道会社に就職をされています。高校での就職活動や入社の経緯について教えてください。
高校内にある求人は限りがあり、学内選考を経て求人へ応募します。ただ、障がい者雇用求人がなかったので、学内選考後に担当の先生より企業へ事情を説明していただき、応募可能であれば参加するという形式でした。応募の許可を得た大手鉄道会社の募集職種は駅員でしたが、「できる・できない」のヒアリングを受ける中で経理部への配属として入社が決まりました。
経理部に7年所属した後、異動を経験されています。障がい者雇用ではキャリアパスの機会が得られず、退職に至るケースも少なくありません。どのような経緯で異動が実現したのでしょうか。
障がい者雇用ではありませんが、同僚が平均3年で異動する中で私の所属も長くなり、新たな業務に挑戦をしたいという想いが強く、異動願いを提出しました。特に否定的な対応をされることはなく、配属先は外出や重いものを持った移動が困難などの「できる・できない」を確認したうえで、メンテナンス部門での部門サポートとして異動しています。
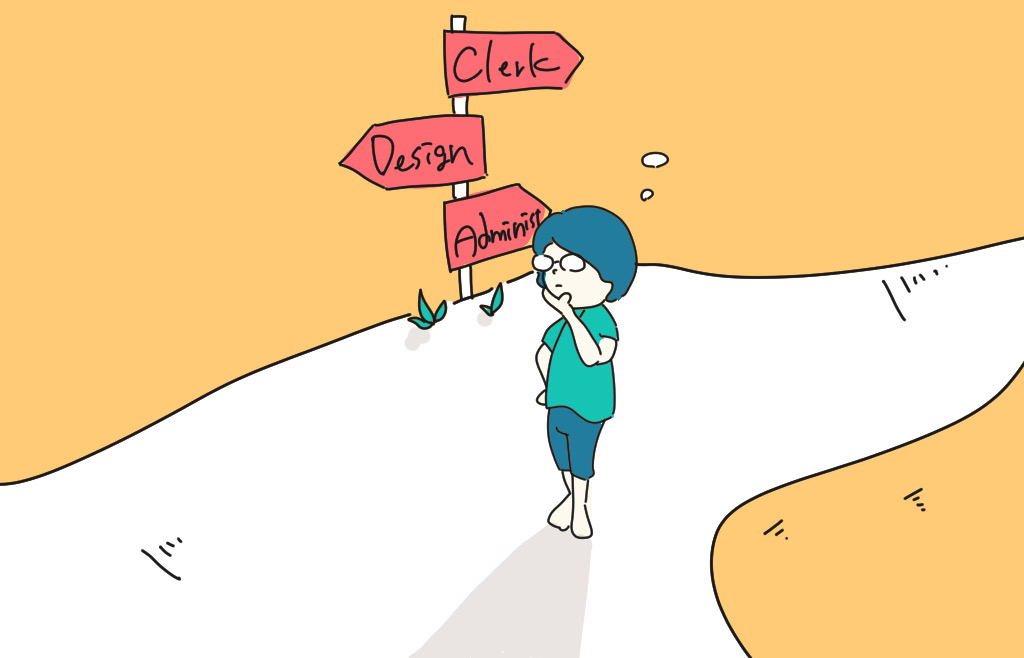
採用担当者のぶっちゃけ質問
セミナーでは参加された採用企業の皆さまからも多くの質問がありました。
Q.配属後面談の頻度や内容を教えてください。
>とくらさん
月に1~2回、1時間程度、直属の上司との面談機会がありました。フランクな関係もあり困りごとは都度相談していたのですが、面談を通じて互いの認識を共有し、より相談しやすい、安心できる関係性ができていたのではと感じています。
>山口さん
定期面談は社員全体にある年1回の評価面談のみでしたが、都度、部署内外問わず気にかけていただいていた印象があります。例えば、片杖のため階段の昇降に不便があるのですが、社長自ら守衛担当に事情の説明とサポートの依頼があったりと優しい配慮を実感していました。
Q.選考において企業にして欲しい配慮はありますか。
>とくらさん
配慮とは違いますが、転職時にある適性検査(筆記試験)が発達障がいの診断テストに似ており、特性があることで選考から排除されているという印象を受けました。適性検査の意図を説明するなどネガティブな印象を与えない注意があると良いかもしれません。
>山口さん
「できる、できない」を聞いていただくことが大切だと思います。私の場合、筋肉の病気のため1回は頑張れるが、2回は頑張れないなど仕事をしてみてわかることも多くあります。選考では難しいかもしれませんが、小さな擦り合わせがあればミスマッチは減っていくのではないでしょうか。また、できなかった場合の代替案や方向転換ができると有難いです。
障がい当事者として登壇を終えた感想
>とくらさん
今回、企業担当者様からの質問に回答する中で、所属した企業での働きやすさを感じていたものの、私自身もどんな部分で働きやすさを感じていたのか、今まで以上に細分化された要素が具体的になった感覚がありました。また、自分の経験を話しながら、山口さんの経験をうかがったことで、N=2の体験ではありますが、働く障がい当事者の共通項に気付くことができました。これは参加企業の皆さまも感じていただけたのではないでしょうか。人事担当者が複数の当事者に直接話を聞く機会はあまり多くないのではと思います。今回のセミナーが少しでも参加企業の皆さまと当事者とのミスマッチを減らしていく一助となれば幸いです。
>山口さん
企業で働いた経験について役立てる場を設けていただいたことに感謝を申し上げます。私自身は今、フリーで働くという道を選択しましたが、まだ企業で働きたかった、というのも正直な気持ちです。企業だからこそ「誰もが働きやすい環境を整備できる」「安心して働ける」双方ともにWin-Winな場が実現できるとも思っています。数多くの企業の皆さまが前向きに、そして真剣に考えているからこそ出てくる質問の数々で、個人的にとても嬉しいと感じました。もちろん短い時間で全ての疑問の解決は難しいと思いますが、少しでもご参考になれば幸いです!貴重な機会をいただき、ありがとうございました。
セミナー参加者のアンケート結果
■セミナー満足度
「非常に良かった」25%
「良かった」75%
セミナー満足度の理由は以下の通りです。
- 当事者の就職に対する視点や求人側の視点が違うという事実がわかったこと
- 一般就労経験のある当事者から実体験を聞くことができたこと
- 気軽に参加できたこと
- 自分が働く会社だけでなく、働く障がいのある当事者の意見が聞けたこと
- 当事者の話を聞く機会が今まで無かったので興味深く聞けたこと
- 当事者から質問への回答があり、採用に関するイメージが作れたこと
- 障がい者採用に関わるのが初めてのため、当事者目線を知る機会になったこと
パラちゃんねるでは、採用企業の皆さまと障がいのある当事者と共により良い障がい者雇用の機会を増やしていきたいと願っています。