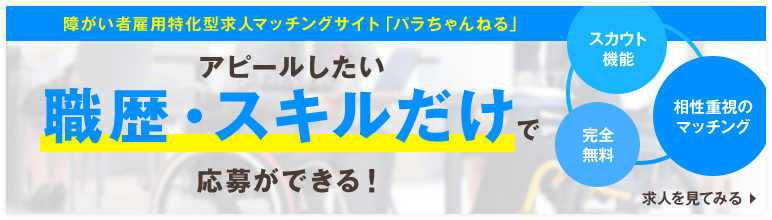16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。これまでの暮らしから振り返る、自立とは何か、依存とは何か。いくらリハビリをしたところで、飛び降りる前の自分に、健常者に戻れるわけではない。リハビリの先にある生活は自立したものと言えるのか。
リハビリの果てに待っているのは自立なのか
すべて終わらせようと思って飛び降りたのに、中途半端に生き残ってしまって、違う意味で人生が終わった。
生まれて初めての骨折が首だなんて、ちょっと笑えない。
神様冗談でしょ、と現状を嘆いたり呪ったりする余裕もない痛みと苦しみが全身に襲いかかってきた。
息ができない、飲めない、食べられない、眠れない。
ようやく眠れたと思ったらセクシャルな夢ばかり見る。しかし感覚を失っているからそれが満たされることはない。
私が何者か、とか、何を思うかとか、そんなこと以前に、「今ここ」に私の肉体があった。
「私」は死にたかったはずなのに、身体は貪欲なまでに生きたがっていた。

1ヶ月くらいで様態が安定して、痛みや苦しみからは開放されたが、それでも3ヶ月はほぼ寝たきりだった。
点滴や呼吸器、看護師や介護士の世話に依存しないと生きられない自分の身体。
おむつを変えてもらい、身体を拭いてもらい、身体の向きを変えてもらい、ご飯を食べさせてもらい……。すべてを他人に任せるしかなかった。
しかも気管切開をして呼吸器を取り付けていたので、声を出すことが出来ず、意志の疎通は口パクか文字盤を指差して行った。これがなかなか伝わらない。中には、気遣いのつもりだったのかもしれないが、伝わってないのに分かったふりをする人もいて、かなりのストレスがあった。
最後のほうは、伝えることを諦め、されるがままになっていったが、せめてやってもらったことに感謝の気持ちは伝えなければ、と思い、意識的に笑うようにしていた。
そういえば健常者の頃はあまり笑わなかったな、と気がつく。
自分の笑った顔が嫌いだった。
「まめちゃんは笑顔が素敵だね」とこのときから言われるようになった。
そうか、誰かに頼ったり、感謝したりする経験が私には足りなかったんだ。頼ってはいけないものだと思っていたし、どうやって頼ればいいのかもわからなかった。笑えばよかったんだ、簡単なことじゃないか。
他人からお世話をされるなんて、申し訳ないとか、屈辱的だ、とさえ思っていたが、何か温かなもので溶かされていく感じがあった。
寝たきりながらもリハビリは始まり、最初はベッドのギャッチアップ(電動ベッドの背の部分を起こすこと)から、ベッド上で水を飲む、歯磨きする、食事する、と自立していき、呼吸器が外れて自分の力で息ができるようになった。声が出るようになったときは本当に嬉しかった。

急性期病院から回復期病院に転院することとなり、本格的にリハビリが始まった。
「リハビリテーション」という言葉は元々中世ヨーロッパにあって、キリスト教カトリック教会から破門された者が再び復帰することを意味していたのだと、理学療法士の先生に教えてもらった。
身分や地位を取り戻し、再び人間らしく生きること。地位とは言わないまでも、1つずつ出来ることを取り戻していく達成感は自己肯定につながったと思う。「リハビリ」は希望に満ちた言葉のように思えた。
もちろん、楽ではなかった。体力的にも精神的にもきついことが多く、すぐにはうまくいかない。
まったくの他人のようになってしまった身体を扱い、コントロールするのは難しい。子供の世話みたいだ。
自律神経障害により、汗が出ず、極端に暑さと寒さに弱く、熱中症になりやすかったり尋常じゃないくらいの悪寒が来て熱発したり。血流の調整も出来ないため、貧血を起こしやすく、車椅子に移乗しただけで意識を失うこともある。
痙性といって、意思に関係なく麻痺した身体に急に力が入り、落車したり、身体をぶつけたり。感覚がないために怪我をしても気がつきにくい。
一番厄介なのが、排泄障害だ。勝手に漏れるし、漏れたことにすら気が付かない。自分より他人が先に気がつくこともあり、恥ずかしい思いをたくさんした。
(この障害の細かいところは中村珍晴さんが詳しく書いてくださっている記事があるので興味のある方はぜひ読まれてください)

特に女性は尿道口が自分からは見えにくいところに隠れており、自己導尿するにも、足を広げなければならないうえ、指先の細かい作業が必要で、指にも麻痺がある私には未だに難しい動作でもある。
トイレの失敗でリハビリを中断せざるを得ないことがあって、もどかしい思いをすることも多々あった。
担当の先生に弱音を吐いたり、いじけてしまったりすることも。
「もちろん、できないままでいい。人に頼ってもまったく構わない。けれど、いつでも人に頼れるわけじゃないからね」
困るのは自分だよ、と先生は言った。冷たい突き放しのようだが、事実そうだ。
何のためにって、自分のためにリハビリをしているのだ。
社会復帰のため、復学するため。自立するため。
そのために、医師や看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカーと、たくさんの大人たちが手を貸してくれる。
親と学校の先生しか大人を知らなかった私にとって、彼らから学んだことは大きい。
どうやって生きていきたいか、一人の人間としての意志をできるだけ尊重してくれて、目的のために必要なケア、必要な情報をふんだんに与えてくれた。彼らは人の人生に寄り添うプロフェッショナルだ。
「今まで税金を払うことなんて馬鹿らしいって思ってたけれど、こうやって使われるんだね。有り難いことだね」
と母が言っていたことを覚えている。社会福祉の有り難みを痛切に感じる。
けれども、いくらリハビリをしたところで、飛び降りる前の自分に、健常者に戻れるわけではない。
私にとってリハビリは、あくまでも健常者に近づくための訓練でしかない。その限界も見えてきていた。
これからこの身体でどうなっていくのだろう。病院の外の世界を意識する時、暗澹たる思いがした。
多くの患者さんがリハビリの結果、日常動作が出来るようになり、家族が迎えに来て退院していく中、私は入院可能な上限6ヶ月が経っても、到底社会復帰はできなさそうだった。