きこえる人のようにしゃべること~その1
音声を出すのをやめたら生きやすくなった
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.9.19

今回は連載コラムです。
「聴覚障害者が音声(こえ)を出すこと」をテーマにしてお話ししたいと思います。
執筆:中川 夜 Yoru Nakagawa
あなたは、1日中、音声を全く出さないで生活することはできますか?
いつも音声を出して意思疎通をはかる聴(こえる)者にとっては、1日だけでも非常に困難なことかもしれません。
むしろ、音声がないと困るのではないかと思います。
「ろう者って、生まれつき耳がきこえない人ってことだよね。きこえないなら、音声でしゃべれない?」

私は聴覚障害者にカテゴリーするろう者です。
実は、聴覚障害者が発声できるかどうかは、幼少期の残存聴力と発音・発声を早期に訓練できたかどうかによります。
家庭の教育方針によって、音声ではなく、手話に特化して育てる人もいます。とはいえ、基本的には発音・発声訓練を受けたことがあるろう者、または難聴者がほとんどだというのが個人的な所感です。
実際のろう者、難聴者、中途失聴者を含めて、聴覚障害者にはさまざまなバックグラウンドを持っている人がいます。
よって、まとめて乱暴に「聴覚障害者ってこういうもの」とは言えないのです。
しゃべれる聴覚障害者もいるし、しゃべらない聴覚障害者もいる。そして、ある程度きこえる聴覚障害者もいて、全くきこえない聴覚障害者もいます。
おそらくここで、「???」となる人もいると思います。
それだと聴覚障害者とは一体どういうものか、ということがわからなくなると思いますので、私のケースをお話しします。
前置きが長くなりましたが、「聴覚障害者が音声を出すこと」について話したいと思います。
「音声」はよくわからないものだが便利

私にとって音声とは、「なんだかよくわからないもの」です。でも、両親と音声でコミュニケーションするときは、「めちゃめちゃ便利だなー」と思っています。
私は発音・発声訓練を受けましたので、ある程度しゃべることはできます。
私の声は聴者のようなイントネーションではないようですが、「聴者でしょ?」と思い違いしてしまうほど聞き取りやすい音声だと聴者の友人から言われます。
基本、同居している親とコミュニケーションをとるときのみ、私の声は重宝しています。
私は3年前から親以外の人には、ほとんどしゃべらないようにしています。理由は、「きこえる人だと間違われると、とっても疲れるから」です。
学生時代はきこえる人に見られている、ということは嬉しかったものですが、だんだん、きこえる人に間違われることは損しかないと気付きました。
相手にきこえる人のように接しても、きこえないのでコミュニケーションの齟齬の回数が何度も起き、その結果「きこえる人に見られるとものすごく困る」のです。
現在、私は補聴器をつけていません。
つけてもきこえないからという理由もありますが、補聴器をつけていると「多少はきこえるんじゃないか?」と勘違いされることが多いのです。
何度も誤解されることに疲れ、補聴器をつけるのもしゃべるのもやめました。
やめるとき、すぐにスパッとやめられたわけではなく、長い間、葛藤しながらの決死の気持ちでした。
閉鎖病室のなかで葛藤しまくった
そのわけは、しゃべることで聴者のコミュニティにギリギリ関われていた手段を失うかもしれないという恐怖からです。
とはいえ、努力したわりにはうまく関われていなかったのですが。それでも、20数年に及ぶ努力してきたことをすべて否定しかねないことでもありました。
そのとき私は24歳くらいで、統合失調症を発症し、その治療のために精神科の閉鎖病室に入院中でした。
他の健常者は、大学生活を謳歌したあとに就活し、新社会人のスタートというなかでした。自分としては一歩も踏み出せてなく、「どこから人生を間違えたのだろう」と非常に不思議でした。
結果的には「しゃべるのをやめる!」と清水の舞台から飛び降りるような気持ちでやめました。
でも、今となるといらない悩みの時間だったなと思います。
長く葛藤していて時間を無駄にした…とまでは言いませんが、日常生活のなかで声を出さないでいる時間が増えると、とても楽になりました。
音声を出すのをやめたら生きやすくなった

なぜなら、音声を出さないことで、聴者は「あ、本当にきこえてないんだな」とわかってくれるので、誤解されることがほぼなくなったためです。
筆談などをしてくれるようになって、やっとコミュニケーションがどういうものかわかりました。
このことを積み重ねていくなかで、「きこえない自分でいいんだ」と思えるようになりました。
そしてめでたし、めでたし…というわけにはいきませんでした。
この続きは、次回お話しします。







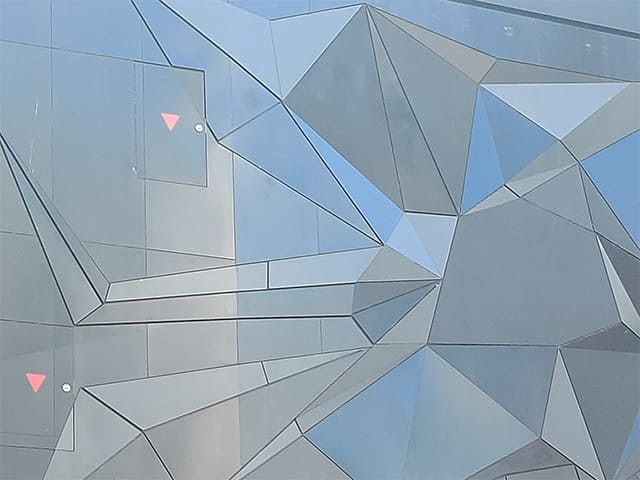

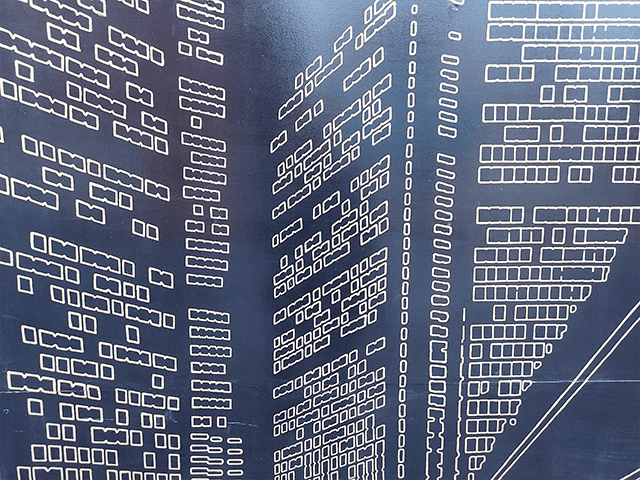


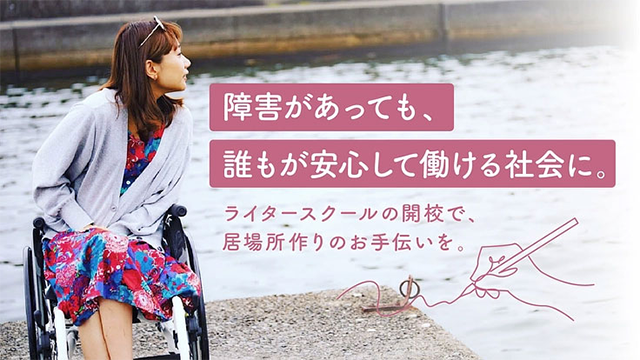


















 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック