メンタルヘルスのための「音楽の聴き方」
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.10.26

現代に生きる私たちが音楽に触れない日は存在しないでしょう。
街に出れば音楽が流れ、テレビやネットでも動画のBGMはどこかしらに使われているものです。
音楽を療法として使うこともあるように音楽は大きな効果をもたらしますが、その効果をどう使うかによって、大きく日常は変わってくるものです。
執筆:いりえ(北橋 玲実)
1週間に18時間。
これは、世界平均の音楽視聴時間だそうです。
(出典:walesonline|世界的に増加している音楽鑑賞に費やされる時間レポート)
確かに、街に出てもネットなどのメディアを見ても、必ずと言っていいほど何かしらの音楽が流れているものです。それ以外にも、スマホや車から音楽を聴く習慣がある方は非常に多いと思います。
サブスクの音楽サービスやスマホが普及していることにより、この数値はますます大きくなっていくでしょう。

音楽は昔から様々な形で人々の生活に寄り添ってきたものであり、皇族への献上品として「音」が使われたり、医学が未発達な時代でも音楽を聞かせることによって苦しみをやわらげるなど、目には見えなくともその存在は確かなものでした。
当然、現代においても音楽療法として疾患治療や緩和ケアの目的で患者の方が音楽を演奏したり聴いたりすることによる効果は広く認められています。

先ほども述べたように現代では多くの人が音楽に日常的に触れていますが、それだけ私たちは無意識のうちに音楽から影響を受けていることでもあります。
場合によっては、音楽によっては怒りを助長するほか、不安を強めて反芻させてしまうこともあります。
実際に音楽の歌詞が犯罪を助長するという研究もあります
(出典:emerald insight|ギャング、音楽、犯罪の仲介:表現、違反、検証)が、そこまではいかなくとも無意識に流れてきている音楽が自分自身にどのような影響(特に悪い影響)を与えているか、ということは強く意識しない方が多いのではないでしょうか。
習慣的に音楽を聴いている方の中にも、「自分がどのような状態のときに、どのような音楽を聴くのか」ということを意識している方はどのくらいいるのでしょうか。おそらく少ないのではないかと思います。
いつもと同じプレイリストを使い回すことが必ずしも身体にいいとは限りません。
なぜなら、曲によってはネガティブな感情を強めて、行動に消極的になってしまったり人間関係を傷つけてしまうこともあるからです。

このように音楽には大きな影響や効果があります。そして、それを週に18時間も聞いている私たちがそれらをうまく使いこなせるかどうかは、思った以上に重要なことなのです。
多くの人が音楽を聴く場合、勉強や作業、運転や買い物をしている間など、「ながら」で聞いている方が多いかと思います。もちろん作業効率を上げる効果もありますが、作業BGMとして音楽を聴くことは、音楽を聴いている自分自身の状態に目が向きづらいというデメリットをもっています。
忙しい現代人に瞑想が重要だという声もありますが、音楽を集中して聴き、聞いている自分自身の状態がどう変化しているか、音楽をどう感じているかにきちんと目を向けることは瞑想と似たような効果があるのではないでしょうか。
たかが音楽、されど音楽。無意識に聴いている音楽ほど私たちの影響は大きいのです。
いつも聴いているその1曲からどんな効果をもらっているのか。その気づきの積み重ねから「この気持ちにはこの曲!」というあなただけの選択肢を見つかるはずです。
たとえば、悲しい気持ちのときは無理をせず、悲しい歌詞の曲を聴いて、気持ちをリンクさせて落ち着かせる。または、逆にすごく楽しい思い出が詰まった曲を聴いて元気をもらう、など。

日々予想のつかないできごとに振り回され、不安や怒りを感じているときこそ、何もしないでただ音楽を聴いてみてください。
そうすればもう一度、肩の力を抜いて前に進む力を与えてくれるはずです。












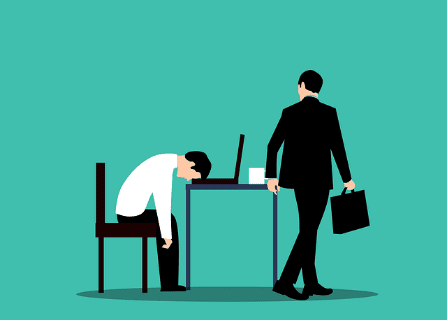

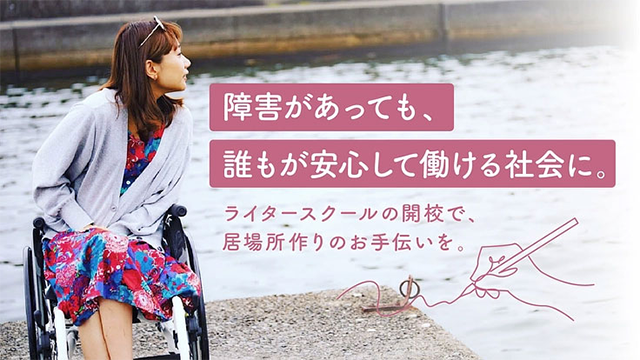









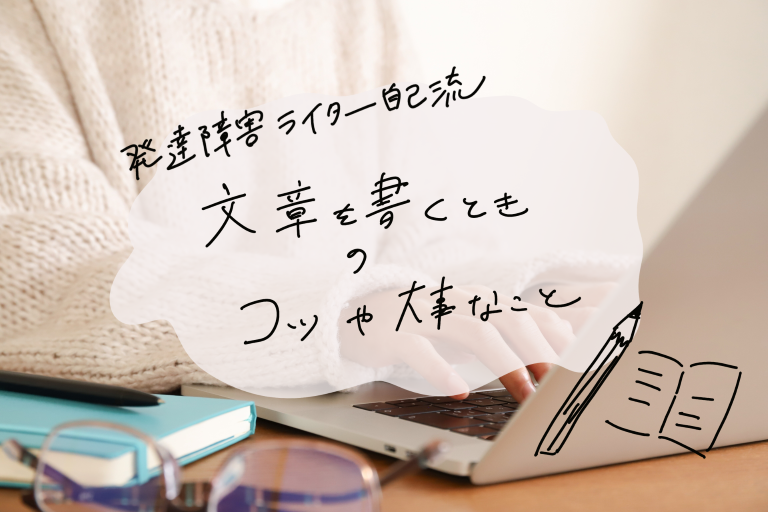









 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック