聴覚障害者とどのように話すか?
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.8.8
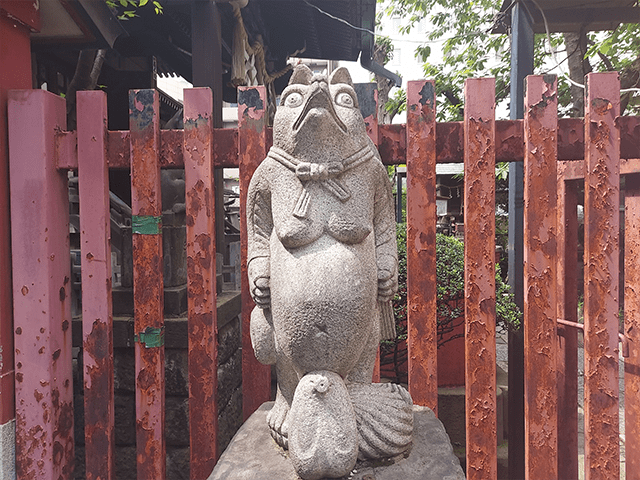
「聴覚障害者とコミュニケーションをどうとればいい?」という話をしたいと思います。
結論として、「正解はない」です。
なんだか、化かされたような、キツネにつつまされたような感じになるかもしれませんね。
「筆談をすれば通じるのかな」
「手話じゃないと通じない」
「ゆっくり話せば通じるよね」
など多様な考えがあると思います。
執筆:中川 夜 Yoru Nakagawa
観察しながらコミュニケーションの方法を変える

こんなことがありました。
とある手話イベントで、補聴器をつけている聴覚障害者に出会いました。
まず、私は手話をしました。
しかし、相手は私の手話を見て、困惑し、申し訳なさそうな顔をします。
口を大きく開けて、ゆっくり手話をしてもますます、相手は恐縮する様子を見せます。
なぜでしょうか?
その人は、手話がちょっとできるだけの難聴者だったからです。
筆談アプリを用い、会話をすることでコミュニケーションは成り立ちました。
この一連の流れを見て、
「じゃあ、筆談すれば通じるんだね!」
と思われた方は少し待ってください。
もし相手が、筆談が難しい小学低学年のろう児だったら?
あなたはどんな方法でコミュニケーションをとるでしょうか?
また、ご年配のろう者、さらに、中年の難聴者だったら?
育ってきた環境が様々な聴覚障害者がいる
このように、きこえない・きこえにくい人には様々な年齢、また育ってきたバックグラウンドの違いがあります。
なので、
「手話さえすればいい」
「筆談さえすればいい」
「口を開けてゆっくり話せばいい」
というわけではないのです。
「じゃあ、聴覚障害者のひとたちはいつもどんなコミュニケーションをとっているの?」
という疑問符が思い浮かぶかもしれません。
私のケースをお話ししますと、私は相手を観察しながら、手話か筆談かを判断します。
これは、聴者同士でも相手を見ながら、声の大きさや声のトーンを調整するのと同じです。
例えば、子どもに向かって話をするとき、優しいトーンの声色で話しかけるように意識すると思います。
また、ご年配の方の場合、様子を見ながら、大きくはっきり話すのではないかなと思います。
これらの観察しながらコミュニケーションを調整することはいわゆる、相手への「思いやり」だと私は思っています。
手話か、筆談か、それとも…
聴覚障害者とコミュニケーションをとるときは、基本的に手話か筆談という認識で大丈夫だと思います。
しかし、なかには難聴者であれば、ゆっくりはっきり音声を発声すれば通じるケースもあります。
私の場合は、手話より、書記日本語(書き言葉)が好きなため、また、類は友を呼ぶのか、周りの聴覚障害者の知人・友人とは基本的にLINEなどのメッセージのやり取りで事足りるという感じです。
もちろん対面では相手が手話ができれば手話です。
相手が日本語対応手話か日本手話(※)かどうかは話しながら、使い分けます。
それが通じないときは、基本的に筆談アプリを使いながらの筆談になります。
口話(口の形から予測して話す言葉を把握すること)はとても疲れるので、あまりしません。
※
・日本語対応手話…日本語の単語に手話単語を一語一語、確実に対応させていくので、(表現するとき)語順は日本語と全く同じになる。
・日本手話…「日本語対応手話」とは本質的に異なる、ろう者独自の手話を意味します(参照: 手話学入門)。
まずは、相手を観察することから

「どんなコミュニケーションがいいですか?」と尋ねるのが難しければ、相手の聴覚障害者の表情を観察しながらコミュニケーションを試してみるのがベターだと思います。
まずは、笑顔で、相手に向かってゆっくり話してみることから始めていいかもしれません。
そのときの相手の表情を少し意識してみてください。
なんだか首をちょっとかしげて困ったような顔をしていたら、筆談に切り替えてみる。
そして、あなたが手話ができるならば、相手の様子を見ながら手話をしてみる。
そのとき、相手からの笑顔が生まれたらそのコミュニケーション方法は適切であるということです。
様々な聴覚障害者がいるので、どういったコミュニケーションが、「その人の笑顔を見れるのか?」を模索しながらやっていくのも楽しいですよ。







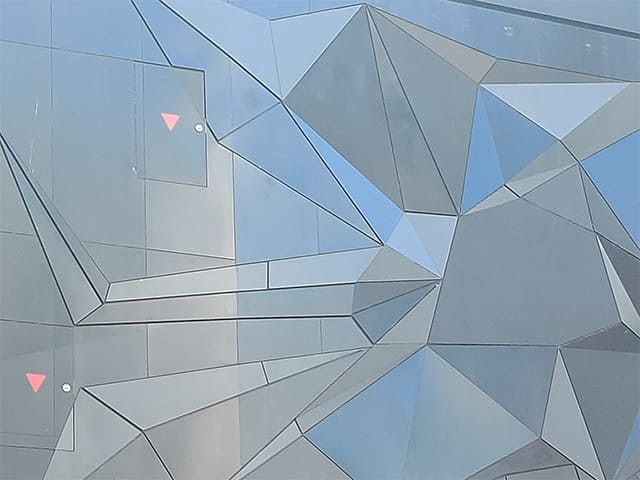

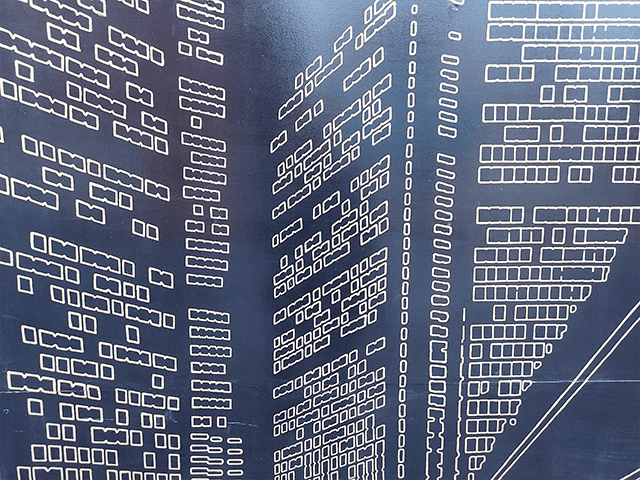


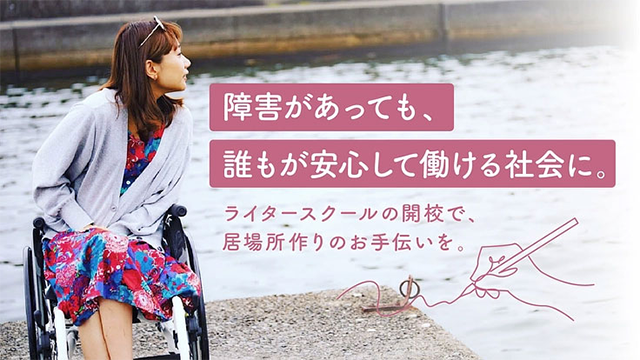


















 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック