発達障害とSOS
![]() 1
1
![]() 1
1
2023.8.30

今回は、発達障害とSOSについて、私個人を例にSOSに出し方とその背景を書いてみたいと思います。勿論、あてはまるからといって、発達障害やその二次障害というわけでもないです。
また、一部、自傷行為やODの内容を含みますが、このコラムは自傷行為やODを推奨しているわけではありません。
執筆:萩 雪希 Yukino Hagi
***編集部より***
このコラムは、あくまでもライター個人の経験に基づくお話です。
一部、自傷行為やODの内容を含みますが、それを推奨しているわけではありません。
****************
SOSの出し方、私の場合
ー 1、突然泣く
個人的にはあまり好まない表現のものの、適切な表現も思い浮かばないため、定型発達と表現しますが、定型発達のかたのSOSとしても認知度はありそうですね。
私は突然泣きます。なんの前触れもなく。
怒られたとき、しんどい時などは誰しも泣きたくなるものだとは思います。ですが、そうではない日常生活の些細な出来事でも、定型発達の方たちが平気な場面や、ただ説明しているだけでも、自分の特性上のことでも、勝手に涙が出てきます。そして結構長く続きます。
ー 2、言葉遣いが荒くなる、気を遣う表現が出来なくなる
私はもともと、言葉遣いが丁寧な方ではないのですが、それがより一層ひどくなり、周囲の人を傷つけてしまうこともしばしばあります。自覚してからは、本当に気を付けてはいるのですが、それでも周囲の人から怒られたり、反感を買っては自分の情けなさに泣く…という負のループに陥ることもしばしばです。
また、これも普段から気を付けてはいるのですが、相手を気遣う表現や発言がより一層難しくなります。例えば、相手がしんどそうにしている時に気が付いて「大丈夫?」などと発言してあげられなかったり、お世辞を言ったり、そう言ったことが出来なくなり、すべてが自分本位、正直すぎる表現になってしまいます。
そう言ったことから、人間関係に亀裂が入ったり、正直すぎると怒られたり…という人間関係においてしんどい状況に自分で自分を追い込んでしまい、その状況がしんどくて体調不良になったりしてしまいます。

ー 3、体調不良になる
これもまた、定型発達のかたにもありがちかも知れませんが、とかく体調不良になりやすいです。身体、精神の両方において。
私の場合、身体的には起立性調節障害、過敏性腸症候群・精神的には双極性障害、解離性同一性障害などですが、病名が付くほどでははなくとも、慢性的な体調不良に悩まされている当事者の方は多いと日々twitterを眺めていて思います。
ー 4、自傷行為、OD(オーバードーズ、過量服薬)
私の場合、これが顕著になるのですが、リストカットなどの自傷行為とオーバードーズの頻度、回数、リストカットなら傷の深さ、オーバードーズなら量が、それぞれ跳ね上がります。

背景にあるもの
私のSOSの出し方は、他の人とは違っているのではないかと思います。そんな表現をする背景にあるのは何か、考えてみました。
ー 自分の中の感情が分かりにくい
気持ちの言語化が難しいというところと重なり、またその一因とも思えますが、私は自分の中の感情が分かりにくいです。
自分は今、嬉しいのか、楽しいのか、はたまた悲しいのか、悔しいのか、情けないのか、疲れているのか、いないのか…どんな感情を抱いているのかを自分に対して一々尋ねないと分かりません。
ー 気持ちの言語化が苦手
パラちゃんねるカフェで、こうしてコラムを執筆させていただいていますが、私は気持ちを言葉で表すことが難しいです。自分の気持ちを適切な言葉で、適切なタイミングで発することが苦手なため、気づいてもらうことも難しいです。
ー 適切なSOSの出し方を知らない、キャッチしてもらえるようなSOSを出せない
上述の通り、自分の中の感情が分かりにくい、気持ちの言語化が苦手、といったことから、適切なSOSの出し方を学ぶ機会がないことで、キャッチしてもらえるようなSOSを出せない、という状態になると考えます。それゆえ、泣いたり自傷行為に及んだり、といったある種「目を引く行動」でSOSを出してしまいます。

終わりに
こうして書いてみると、私が思いつく限りでは発達障害に特有のSOSというのは少ないのかと思いました。ですが、原因を考えたとき、そこには発達特性が絡んでいると考えられました。
SOSを伝えるためのこのような行為は、周囲を困らせようと思ってやっているのではなく、むしろ自分自身が本当に困ってやっています。
伝わりづらいとは思いますが、上記のような背景などを理解して、見守っていただけると嬉しいです。
今は少しずつですが、正しい・分かって貰えるSOSの出し方を学んでいます。
このコラムが皆さんにとって有益であれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!










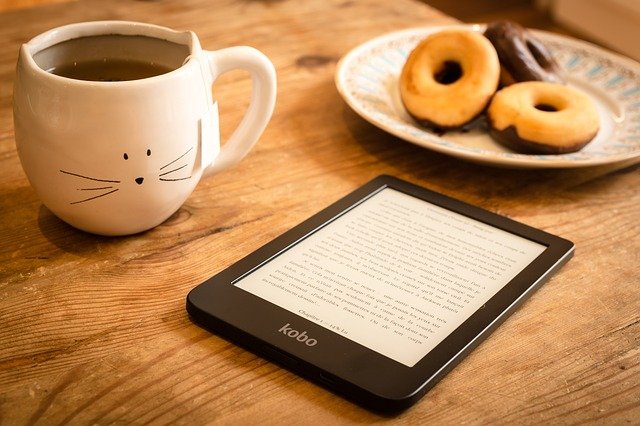
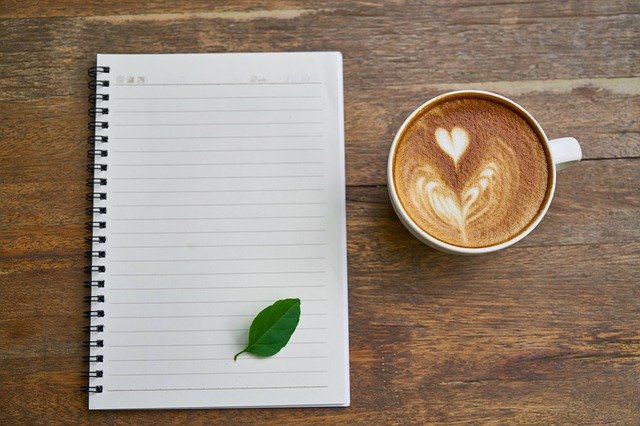





















 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック