障害特性の影響で計画を立てるのが苦手な私が、働きながら資格を取得した方法
![]() 1
1
![]() 1
1
2023.9.23
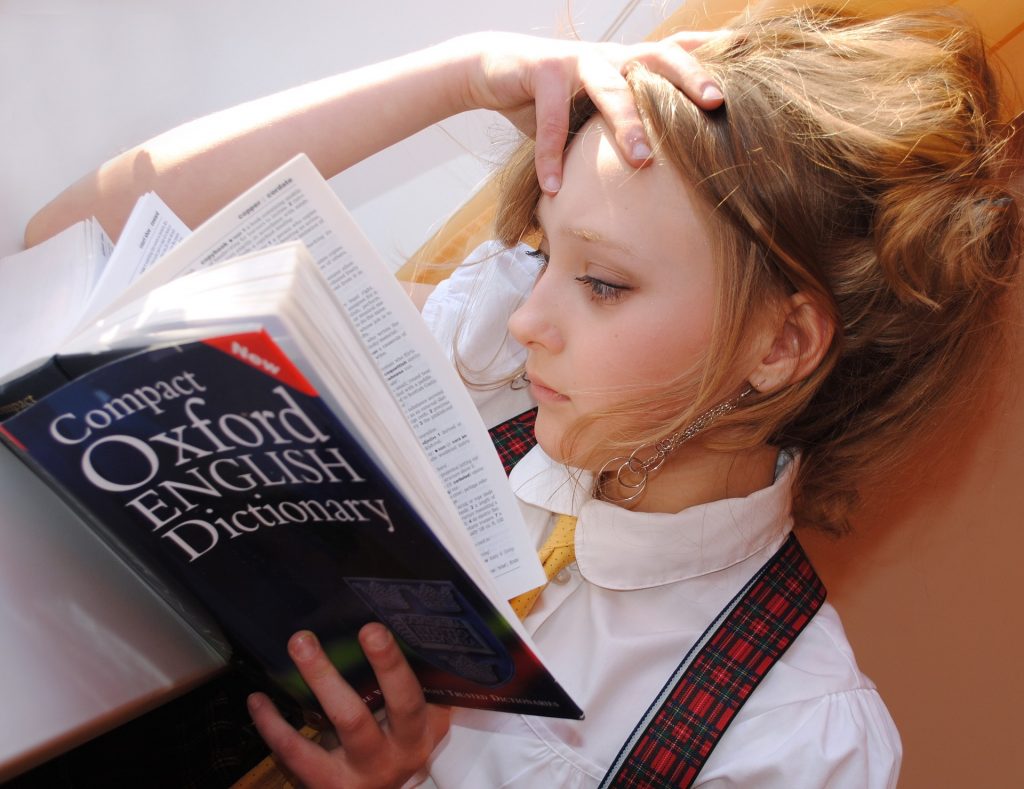
私は今の会社に入ってから資格を3つ取得した。勉強が苦手な上にスケジュール管理も下手な発達障害当事者の私にとっては、仕事をしながら資格勉強するのはなかなか簡単ではなかった。今回は私が勉強する際に気をつけたことや時間の使い方などをお話ししていこうと思う。
執筆:月尾 いる
はじめに
私は今の会社に入ってから資格を3つ取得した。ITパスポートとWebライティング能力検定と文章能力検定である。最初は、「せっかく会社が試験代や報奨金を出してくれるのなら資格取得補助制度を活用しようかな」くらいの気持ちだったが、今となっては資格を取得したことで自信もついて良かったと感じている。
とはいえ、勉強が苦手な上にスケジュール管理も下手な発達障害当事者の私にとっては、仕事をしながら資格勉強するのはなかなか簡単ではなかった。
しかし、なんとか無事に資格を取得できたので、今回は私が勉強する際に気をつけたことや時間の使い方などについてお話ししていこうと思う。
計画が立てられない私の時間の使い方
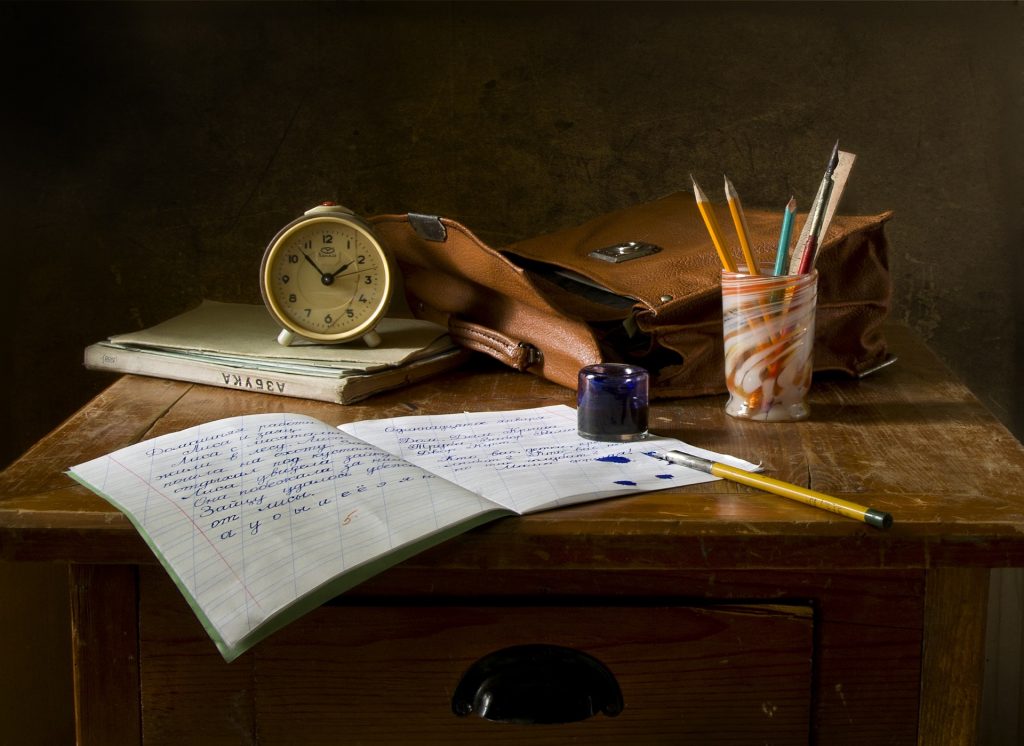
子どもの頃、あなたの周りにも夏休みの宿題を始業式ギリギリまで放置している人はいなかっただろうか?
なんとなく察しはついているかもしれないが、私はモロにそのタイプだった。
夏休みの宿題を遂行するためにはまず計画を立てる必要があるけれど、「計画の立て方」からしてよくわからなかったため、計画表も宿題も白紙のまま放置して遊び呆けていた。
気がついたら夏休み後半に入っており、私よりも周囲が慌てだす。もちろん、毎回怒られるのだが「宿題を終わらすための計画の立て方」という根本的なことを学習していないため、毎年同じ過ちを繰り返す…これが宿題を放置してしまうメカニズムだったと大人になってから気づいた。
月日が流れたとはいえ、そのまま大人になった私が綿密な計画を立てられるわけがない。だから、資格を取得しようと決めたときも勉強時間や計画はざっくりと決めるしかなかった。
たとえば、大体どの資格も平均して1日2.5時間くらいは勉強していたが、具体的な勉強時間は決めておらず、「1日のどこかの時間で目標を立てたところまでは終わらそう」というスタンスでいた。
いい加減なことが嫌いな人にはむずかしいかもしれないが、ときには、「どのような計画を立ててもイレギュラーなことはやってくる」という開き直りが必要かもしれない。
たとえば、私がITパスポートを受けたときは試験日まで4ヶ月しかなかったので、「いつ頃までにテキストを読み終えていればいいのか」と「現実的に自分が1日あたりどの程度までならテキストを読めるのか」という2点を考える必要があった。
テキストの中身は全部で16チャプターあったので当初は、「1日1チャプターずつ進めていけばいいかな? 」と考えていたら案の定体調を崩すというイレギュラーな事態が発生。1ヶ月ほどろくに勉強ができなかった。
そこで、試験勉強再開後は過去問を解く時間をできるだけ確保するためにも、まずはテキストを読み終えることに全集中した。
オンとオフの切り替えが苦手だからこそ意識したこと

幸い、ITパスポートを取得した時期はあまり忙しくなかったことや、会社の人がスキマ時間に試験勉強をしてもいいといってくれたので追い込まれるほどのしんどさはなかった。
しかし、1ヶ月間体調不良で勉強できなかった分の不安、休日の勉強時間の負担がなかったといえば嘘になる。また、障害の特性上オンとオフの切り替えやメリハリがつけにくいこともしばしばあった。
そこで、やる気の出ないときは、「少しだけでも始めよう」と自分に言い聞かせて勉強に取りかかることにした。この考え方は、以前ネットで話題になっていた「自分のやる気を起こすスイッチはボタンではなくつまみでできている」という話に由来している。
自分のやる気は部屋の電気をつけるボタンのように即座にオンとオフで切り替えようとせず、つまみを回すように徐々に上げていくことを意識するとうまくいくそうだ。つまり、最低限のことでも実際に取りかかっていけば徐々にモチベーションがあがっていき、最終的にはタスクをこなせるという理屈だ。
この方法はあまりやる気がでないときにも効果を感じたのでおすすめだが、体調次第ではまったく集中できない場合もあるので無理をしないことが大切だろう。
また、勉強に集中していると止めるタイミングの見極めがむずかしいが、疲れが出ると次の日に影響するかもしれないので目標のタスクを終えたら切り上げることを意識していた。
得手不得手分野を把握して余裕を持って取り組もう
私は計画を立てるのも苦手だが、たとえ、計画を立てたとしてもその通りに実行するのが負担になるタイプだとも思う。そのため、「これくらいの期間を試験勉強に当てたら、試験当日に間に合うかな? 」というおおよその感覚を大切にしていた。
体感的なことは個人差があるので、他の方へは上手く説明できない部分もあるが、過去の失敗経験や自分の特性などを考えた上で余裕を持ってスケジュールを組むように意識している。ケースバイケースだが私の場合、通常の人が予定する1ヶ月以上は多めに見積もることが多い。
また、試験の申し込みは期日に余裕を持って行うことも大切だが、あまりにも早い段階から申し込むとプレッシャーがかかる場合もあるので注意している。
他には、自分の特性や得手不得手を知っておくことも大切だ。たとえば、一口に試験といっても暗記系・計算系・論述系などさまざまだが、それぞれに向き不向きはあると思う。ちなみに、私は昔から理数系科目が壊滅的なので計算系が一番苦手だ。
ITパスポートにも一部計算問題があり、過去問では解説を見ながら解いたものの本番はまったくできなかった。計算問題よりも暗記系が多かったのと、すべて4択式だったので勘で回答した問題がいくつか当たっていたのかもしれない。つまり、運が良かったのだろう。
後悔はしていないが、慣れないうちは苦手分野よりも自分の興味がある分野・得意分野の資格に挑戦した方がいいとも思う。
取得しても意味がない資格は無駄なのか?
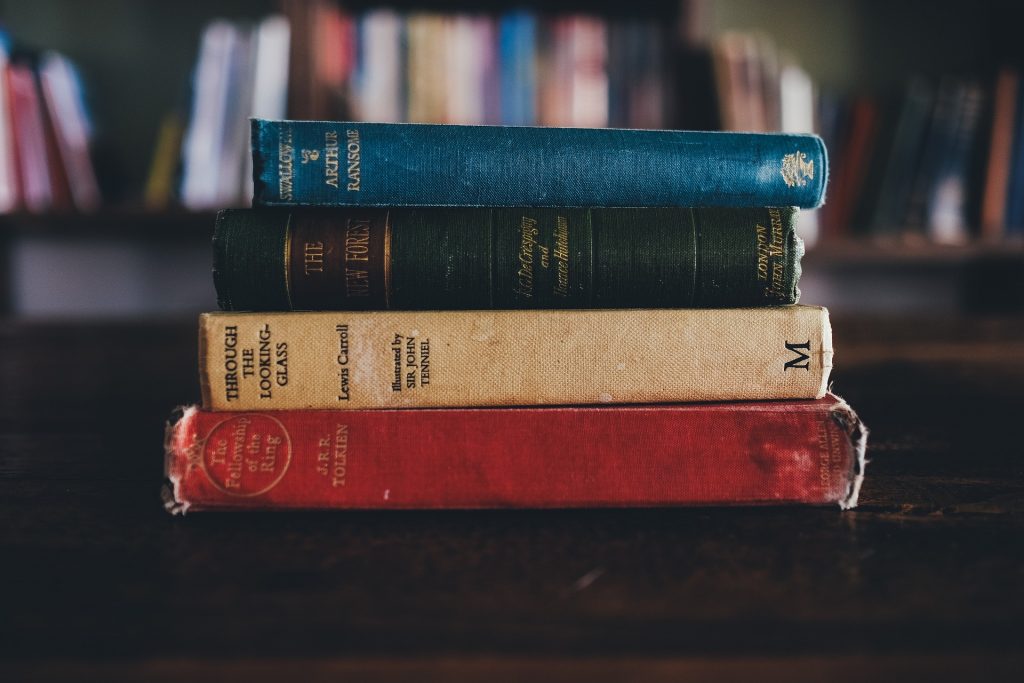
「◯◯資格は取得しても意味がない」という声をネットやリアルで聞いたことがある人もいるだろう。私も昔「この資格は持っていても意味がない」とはっきり言われたことがある。
「実務や就職活動へ役立つかどうか」という視点は大切なので、間違いではないかもしれないが、個人的には気になった資格を取得することは無駄ではないと思っている。
私が取得した3つの資格はどれも実用的ではないと言われているが、取得したことで「自分にもできるんだ」という自信につながった。それに、「次はまた違う資格を取得してみよう」という前向きな気持ちも湧いてくる。
だから、「働きながら資格取得できるだろうか?」と悩んでいる方は、テキストや過去問に「少しだけ」取りかかることをおすすめする。先ほどのスイッチの話のように徐々にやる気が湧いてくるかもしれないし、やる気が出るとモチベーション維持にもつながるので合格できる可能性も高まるだろう。気候的にも過ごしやすい秋は集中力も高まるので、目標を決めて勉強をはじめてみてはいかがだろうか。










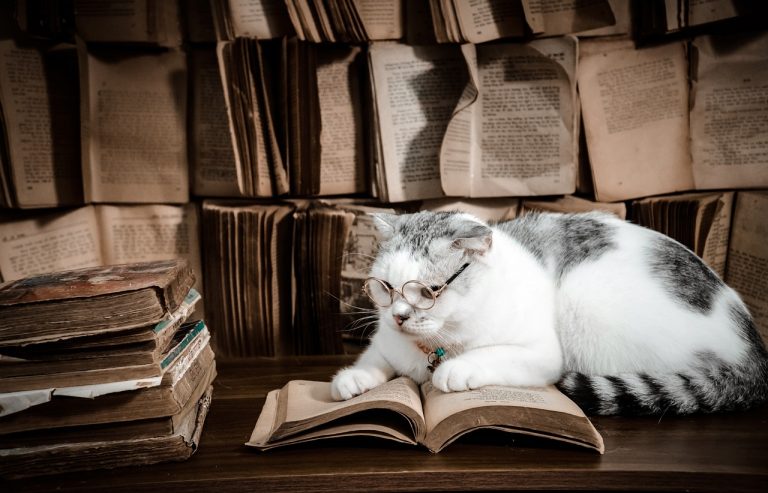
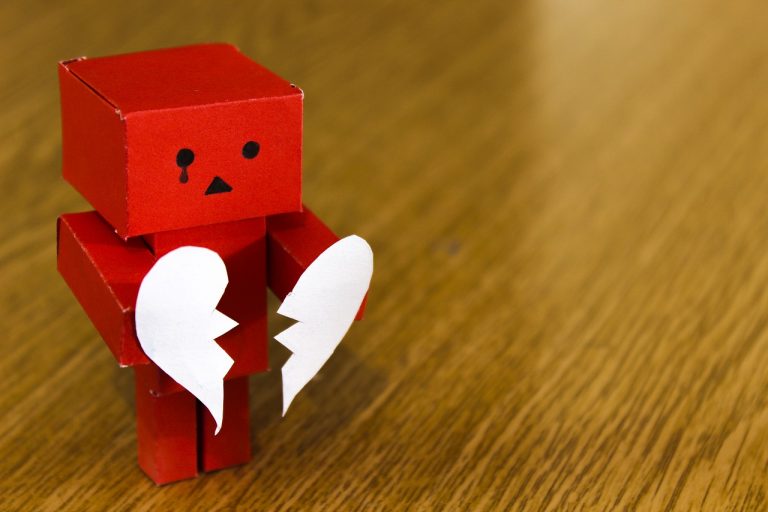







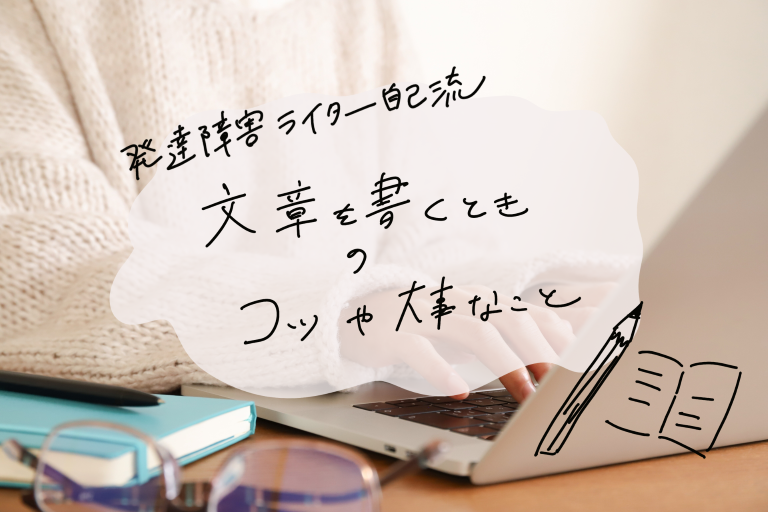

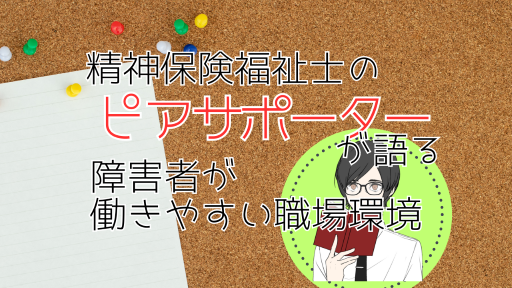
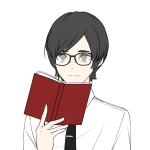
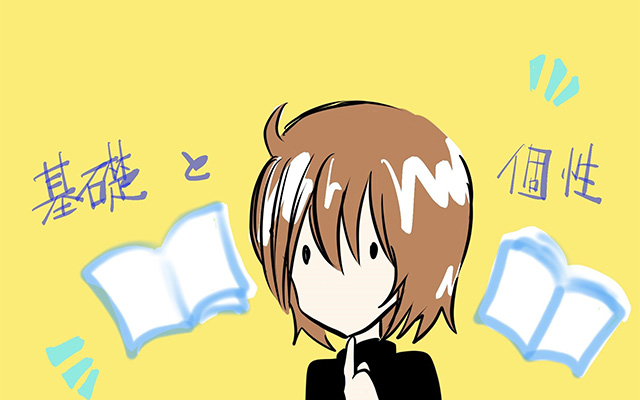








 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック