障害者の私が就活で「内定」をもらうために心がけたこと
![]() 1
1
![]() 1
1
2023.4.24

私は「生まれつきの障害者」なので、働く上で制限があることは理解していました。
ただ「働く」ことが、こんなにも難しいとは思っていなかったのです。
今回は私が新卒の時に経験した就活にスポットを当てて書いてみます。
執筆:山口 真未 Mami Yamaguchi
障害者にとって、人それぞれ「できること」「できないこと」がありますよね。
ただ私からすれば、それは人として当然とも思っています。誰しも得意分野・苦手分野があるのと同じだと。
だから、まさか自分が「働くこと」、会社や人に「働けると思ってもらうこと」にハードルがあるとは思ってなかった、というのが就活を始めて感じた正直な感想でした。
それまでバイト経験もなかったので、就活を始めて働くことをリアルにイメージした時に、ようやく壁が無数にあると気づきました。
とは言っても、私は高卒で入社したため、大学生の就活とは少し異なります。あくまで学校を通して行うので、先生が企業とやり取りを行う方式。
商業高校に通っていたこと、さらに団塊世代の大量退職前であったため、比較的に企業が採用に前向きで、求人数だけなら就職希望者の全員が就職できるくらいには、余裕もありました。
企業の推薦枠に対して希望者が複数いる場合は、学校内で会議が行われ、成績等で決められました。
そんな中で私は、企業に面接すら断られることもありながら、ようやく面接を受けられた会社に就職できました。
その内定をもらうまでの過程で、おそらく「障害者だからこそ」のポイントがありました。それを振り返ってみたいと思います。
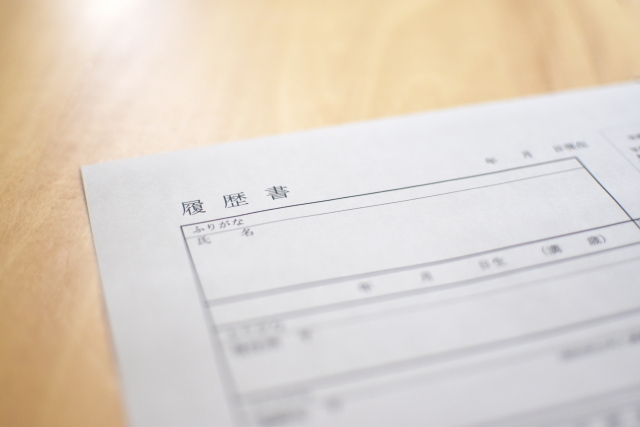
求人票で見ていたポイント
商業高校とはいえ、色々な会社から求人があり、職種も多種多様。事務系のお仕事はもちろんのこと、販売や営業、配達系のお仕事もありました。銀行や信用組合も多く、当時はリーマンショック前だったこともあり人気企業の1つでした。
私が求人票で見ていたポイントは、主に3つ。
- 1、お仕事の内容
- 2、勤務の場所
- 3、周辺の環境
順番に詳しくご説明します。
ー 1、お仕事の内容
身体に障害のある私は、オフィス内でのお仕事が必須だったため、事務系のお仕事を中心に探していました。
探しつつも気になった企業のお仕事は、先生に仕事の一連の流れを聞いていました。
私の障害の特性上、重いモノが持てない、立ち上がりが難しい所があるなど、細かい部分があります。
1日の仕事の流れの中で、人に手伝ってもらえれば出来る余地があるのかということを気にしつつチェックしていました。
ー 2、勤務の場所
住所からわかる勤務場所です。勤務場所がどんな建物なのかをチェックしていました。
例えば建物の入り口はどうなのか、もしビルなら古い建物の場合は階段しかない可能性が高いです。
私にとって階段を上ることは可能とはいえ、時間もかかる上、体力も削られるので3階以上ならエレベーターは必須でした。
ー 3、周辺の環境
最後に周辺環境です。
自宅から勤務場所へのルートと言った方がシンプルですが、駅がどこにあり、勤務場所までの道のりはどうなのか。
電車を利用するなら、乗り換えが必要なのか、通勤時間帯の込み具合はどうか。道のりの途中で階段や急な坂はないかなどをチェックします。
また駅から会社までの距離も重要で、バスに乗らなくては行けないような距離はNGでした。
このチェックポイントを見つつ、企業を絞って、ようやく面接です。
その面接も障害者の私だからこそ、と先生に厳しくご指導いただきました。

面接の動作は気にするな!
面接には、独特の面接マナーがありますよね。
ドアを何回ノックして、どこで礼をするか、などです。
マナーも大事ですが、私にはそれ以上に気を付けるポイントがあると先生から言われていました。
その先生は授業時から怖い先生で知られていたのですが、私は目をかけていただいたこともあり、本音でかつ厳しさをもってご指導いただいたことは、今でも覚えています。
その中でも印象的だったのが、動作のお話。
私にはマナーと分かっていても、どうしてもできない部分がありました。
例えば一礼するにも、30~45度の角度でお辞儀するのが難しいこと。
指をピンと揃えるにも、限界があること。
また極めつけは椅子に座った後、自力では立てないため必然的に面接官に手助けを求めなくてはならないことです。
「できない」ことが、その時点でマイナスとなるのではないかと不安が募るばかり。
でも先生からは
「そんな動作は気にするな!きちんと型さえできていれば、お前の場合はOKだ。それくらい面接官だってわかるし、減点などしない!」
と言われました。
当時、とても衝撃的だった言葉ですが、今でも意識しています。
簡単にいえば、マナーを理解して守る意識さえあれば、その気持ちは相手に伝わるということ。

そもそも面接は、マナーを厳格に守れるかを判断する場ではないはずです。
書類では伝わらない部分で「あなたと働きたい」と思ってもらえるかということが大切ですよね。
例えば、明るく元気なのか、前向き思考か、それとも思慮深く考えて行動するのか…など、自分という人間性を知ってもらう場でもあります。
そのためマナー以上に意識して、「自分の言葉で正確に伝えられるようにしろ」と先生に言われたことがあります。
とくに「障害を説明できるか」ということ。
病気の内容を説明できるのは当然のこと、「できること」「できないこと」「手助けが欲しいこと」など。
具体的にわかりやすく、障害や病気の知識がない人に説明をしなければなりません。もちろんオフィスのハード面など、物理的な課題などは、持ち帰りになることもあると思います。
面接官とはいえ、1人の人間であり、障害の知識があっても、分からないことは多いはず。採用した後に一緒に働けるのか、働く場を提供できるかと不安もあるかもしれません。その不安を少しでも消さない限り、一緒に働くのは難しいですよね。
そのための説明を、自分でできるか。
また相手が欲しいと思っている情報を話せるかどうか、が大事になります。
面接官が知りたいのは障害があることへの苦労話ではなく、働くために必要な情報。その情報をいかにわかりやすく、かつネガティブになり過ぎずに伝えられるか。
先生からは面接に挑むためのマインドを教えていただき、自分の言葉で説明したことが相手にどう伝わるか、と何度も練習を重ねました。
そして、いざ面接の当日。
先生の予想通り、私の採用面接は志望動機よりも、障害のことやどんな仕事ならできそうか、相談会のようになりました。
でも、先生に教わって練習を重ねたとおりに回答したことで、「内定」というかたちでその会社とのご縁ができたと今でも思っています。

就職のハードルは高いが、超えられないことはない
「働く」ということは、それまでの学生生活とはガラッと変わります。
自分がどんな価値を会社へ提供できるか、そのアピールの場が面接です。
障害を持っている場合は、できないことを話しつつも、できることをアピールするべきだと私は思います。できないことばかりをアピールしても、働くイメージができないですから。
まずは自分が働ける状況かを求人票で、自分なりに見極めること。
面接の場では、自分の障害をわかりやすく、ポジティブに伝えること。
私が意識したこの二つ、少しでも参考になれば嬉しいです。
Text by
Mami Yamaguchi
山口 真未


1990年生まれ。障害者ファイナンシャルプランナー(FP)。生まれつき”筋ジスの仲間”と言われつつも、正式な「ベスレムミオパチー」の診断は大人になってから。高卒・障害者雇用で大手鉄道会社の事務で10年以上勤務したが、病気の悪化により退職。そこで改めて、お金の大切さに気付く。現在は、障害者だからあるお金の悩みと寄り添いたく、障害者FPとして活動中。




























 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック