【5/23は難病の日】あなたの隣にいるかもしれない、誰かの難病を知る
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.5.15

5月にはさまざまな病気の啓発デーがありますが、5月23日は難病の日が制定されています。
難病の日とは、どのような目的や経緯で制定された日なのでしょうか?詳しく解説していきます。
執筆:xu
難病と聞くと、誰もが「大変な病気」「自分にはあまり関係のないこと」と感じると思いますが、実は難病は身近な病気であることをご存知でしょうか?
人口の一定の割合で発症すると言われている難病。ひょっとすると、あなたの周りにも難病を患っている方がいらっしゃるかもしれません。
そして、自分が突然難病になってしまうことも。実は身近な存在である「難病」の、記念日についてお話させてください。
実は身近な「難病」

難病の日は、2014年の5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」、通称「難病法」が成立したことを記念して制定された記念日です。
治療法が確立していない病気や研究途中である病気、そして、辛い症状に悩まされていながらも指定難病ではない病気など、難病にはさまざまな問題があります。
難病の日は、そんな患者や患者の家族の思いを多くの人に知ってもらう目的で制定されました。
難病にはたくさんの種類がある

一口に難病と言っても、「難病」という名前の病気があるわけではありません。
難病とは一般的に、
- 原因がわからない
- 治療が困難
といった病気のことです。
ちなみに、指定難病として登録されている疾患は、令和3年11月1日現在で338種類あり、指定難病に登録されていない疾患もあります。
難病の中には、原因がわかっているものや治療法が確立されているものがありますが、新しい難病や症例が少ない難病もあり、今後の研究が必要となっています。
難病法とは?

難病法とは、難病患者を救済することを目的として、原因や治療法の研究・治療費の助成などを定めた法律のことを指します。
徐々に理解や支援の手が向けられるようになった難病への研究が進んだことで、数々の難病の治療が可能となり、予後は飛躍的に改善されました。
筆者が疾患しているSLE(全身性エリテマトーデス)も、昔は助からなかった病気です。
そして、2014年5月23日に制定された難病法では、指定難病の対象疾患を大幅に増やしたことで、いくぶんか難病患者への福祉が整いはじめましたが、軽症患者への支援がなくなってしまうなどの問題もありました。
現在では、難病患者に対する理解や共生社会の実現の他に、就労や働けなくなってしまった人への救済制度など、さまざまな問題を抱えています。
これらの問題に対し、難病法の改正をすることで、よりよい難病対策が目指されています。
難病を理解しよう

このように、難病に関する問題は時代を追うごとに改善されていますが、まだまだ不完全な部分があります。
難病法の制定に伴い、難病が障害者総合支援法の対象になったことから、難病患者が障害者手帳がなくても就労移行支援施設の利用が可能になり、さまざまな福祉支援を受けることが可能になりました。
ですが、一般企業への就労が困難であったり、働けない難病患者に対する支援が生活保護しか残されていない場合など、まだまだ課題はあると当事者としても感じています。
また、目に見えない疾患であることから、誤解や偏見の目で見られることも少なくないです。
あなたの周りにも、難病の方がいらっしゃるかもしれません。そして、自分もある日突然難病になってしまうかもしれません。
「自分には関係ない」ではなく、難病を抱えている方が実は身近にいらっしゃること、そして自分も突然難病になってしまうかもしれないという、当事者意識を持っていただければ幸いです。







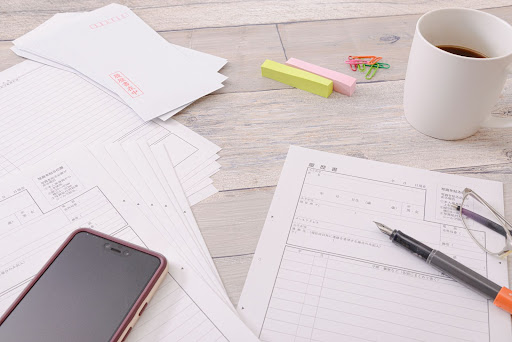



















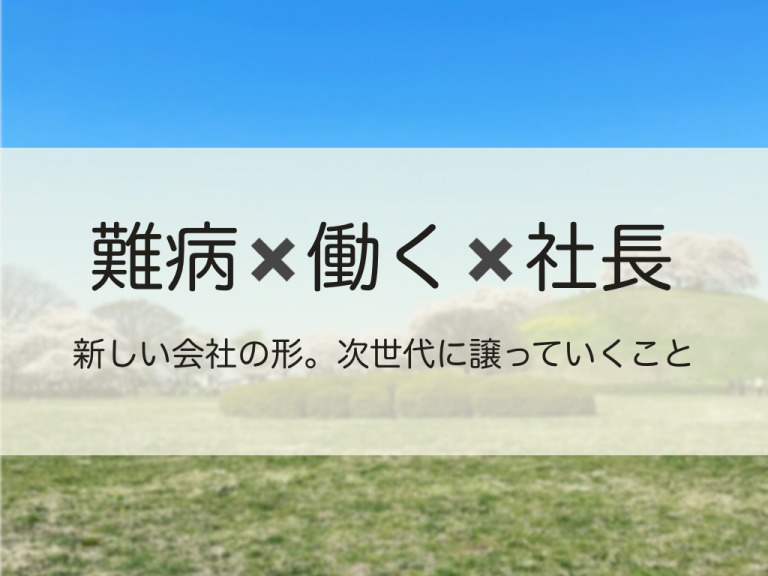








 新着記事
新着記事
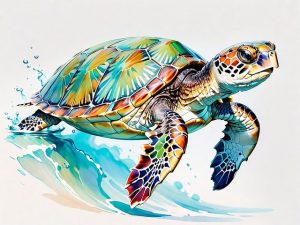



 いますぐチェック
いますぐチェック